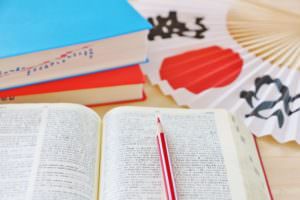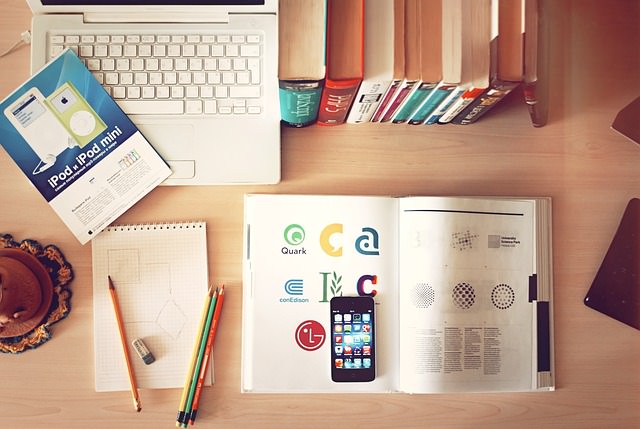
こんにちは!
今日は、上智大学が気になっている方のために、上智大学の基礎知識、一般入試科目、英語の対策などをまとめました!
国際的なイメージのある上智大学、早速確認していきましょう!
Contents
上智大学の基礎知識。偏差値や授業料は?

上智大学各学部の基礎知識について書いていきます。
まず、上智大学には、多数の学部が存在します。
文系の大学のイメージですが、理工学部も古くからある大学になっています。
偏差値は、文系が67で、理系が62と、上位私立の早稲田、慶応、国際基督教大学などの次に位置する難易度になっています。
受験するには、それなりの偏差値が必要になってくるでしょう。
上智大学、学部ことの偏差値は?
学部ごとの偏差値というのを紹介しますので、受験の際に参考にしてみて下さい。
まず、河合塾の偏差値表で確認すると、神学部が57.5になります。
上智大学の中では、低い偏差値になります。
そして、文学部が62.5~65になっています。
英語学科が最も高く、続いてドイツ語学科になっています。
さらには、総合人間学部は、57.5~67.5になっています。
その中でも、教育学科、社会学科が最も高い偏差値になっています。
総合グローバル学部は、総合グローバル学科のみで、67.5となっています。
法学部は、65になります。
法律学科、国際関係法学科、地球環境法学科どこも同じ偏差値になっています。
さらには、経済学部は、65で、経済学科、経営学科とも同じ偏差値になっています。
理工学部は、62.5となっており、物質生命理工学科、機能創造理工学部、情報理工学科ともに同じ偏差値になっています。
上智大学に入る費用はどれくらい?
上智大学に入るのにかかるお金は、入学金が20万円になり、学費が120~180万円となっています。
学部により価格が変わってきます。
そして、上智大学の昨年の就職率は、74.4%となっています。
一生懸命勉強して、受験をするだけの価値のある大学なのではないでしょうか。
上智大学の一般入試科目は?

上智大学の受験科目とその配点について紹介していきます。
受験する際は、参考にしてみて下さい。
神学部の一般入試科目
神学部の神/一般学科別は、3教科(350点満点)となっています。
【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【地歴】世B・日Bから1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150)
となっています。
小論文、面接は、一次試験合格者のみになります。
文学部 哲学学科の一般入試科目
文学部の哲学学科/一般学科別は、3教科(410点満点)になります。
【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
となっています。
総合人間科学部 教育学科の一般入試科目
3教科(350点満点)となっています。
【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
となっています。
経済学部経済学科の一般入試科目
経済学部経済学科の一般入試科目は3教科(350点満点)となっています。
配点は、
【国語】国語総合・現代文B(古文・漢文を除く)(100)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150)
となっています。
外国語学部英語学科の一般入試科目
外国語学部 英語学科の一般入試は3教科(350点満点)となっています
配点は、【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
となっています
上智大学 入試英語の対策は?
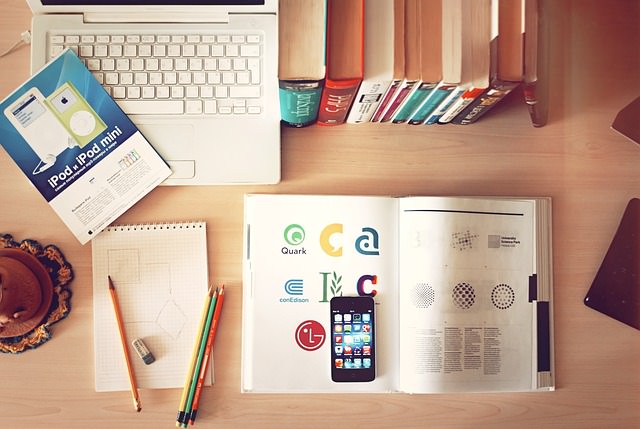
上智大学は、他の大学と比べて英語が出来なくては、受かることができません。
受験において、英語の力を付けていくということがとても大切になってきます。
どのような対策を取ったほうがいいのでしょうか?
長文問題はかなりオーソドックス
まず、上智大学の英語の長文問題というのは、極々オーソドックスな問題になっています。
内容把握と、空欄を生めるような問題が出されています。
必要なのは英語の長文を読解する力。
上智大学の長文は、すらすらと読める簡単な長文から、何を言っているのだろうという難しい長文まで出ます。
まずは、一文一文しっかりと理解していきましょう。
そして、難しい長文は、最後まで読んでも、何の話だったのだろうということになることが多いです。
ですから、著者の意図やテーマというものをとらえながら読解していくことが大切になるでしょう。
内容一致の問題が出てきますが、解き方としては、問題を読み、その分を探していく。
答えたら、また、問題を読んでいく。
という解き方をしていくのがいいでしょう。