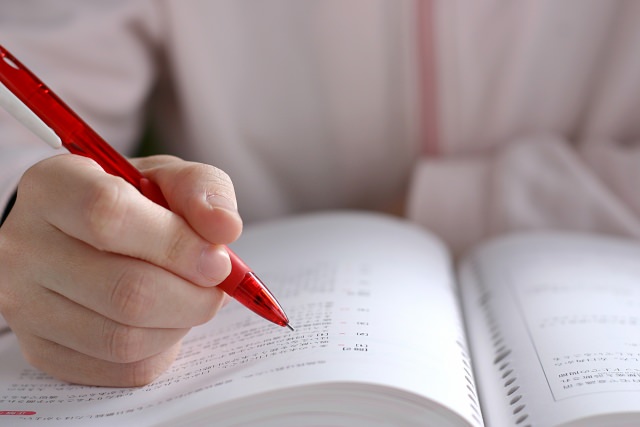
こんにちは。佐藤圭です。
今回は大学受験で必要な読解力についてご紹介します。
レベル別で焦点を当てていきますのでぜひ参考にしてください。
GMARCHの英語
受験生に人気のマーチと呼ばれる大学群ですが、実際どんな対策をしていけばいいのでしょうか。
ざっくり言ってしまうと、複雑な構文把握や専門的な見方は必要なく、語彙力があればしっかり解ける構成になっています。
いわゆる努力型、力技で高得点が見込めます。
今回は長文読解に焦点を当てているので、英作文や文法に関しては割愛しますが、どちらにせよほぼ全てが基本的な知識で構成されています。
早稲田、慶応、上智の英語
最難関の私立の読解問題はどうでしょうか。
語彙は前述の大学に比べて難易度は上がります。
さらに語彙だけでなく、複雑な構文と未知単語の類推力など、単純な英語力だけでは到底対応できないレベルです。
ここを勘違いして、難しい単語が出るからと余計な単語を覚えたり、他の科目を犠牲にしてまで英語をやったりと努力をしているのに合格が近づかないという事態に陥ります。
各種参考書や傾向を確認し、どんな力が必要なのかをしっかり把握しましょう。特に学部ごとの違いや特性もあるので、最短距離で学習ができるように対策をしましょう。
最難関の大学は「がむしゃらに努力すればいい」では合格しません。
受験は戦略であるということを入試問題を通して教えてくれます。
東大をはじめとする国立の英語
結論から言えば語彙の難易度そのものはGMARCHレベルです。
少なくとも、早稲田、慶応のような高い語彙は必要ありません。
そういった私立最難関の大学を受験する生徒が東大や国立の英語の問題を見たときに「え?東大の問題ってこんなに簡単なの?」というほどです。
残念ながら科目数の関係で私立志望の人は国立の受験そのものが難しくなりますし、使われている単語がそんなに難しくなくとも、設問のレベルが高いのでどちらが易しい難しいというのは一概には言えません。
しかし国立系の入試問題はどれだけ多くの単語を暗記したかではなく、未知なる単語の類推や少しひねった設問で受験生を悩ませます。
単純な英語力ではなく、思考力や問題を見る視点が大切です。私立のスピード処理型の問題ではなく、じっくり考え深さが求められる問題になっています。
読解力とは何か?
「本を読む子は読解力が上がる」ということを聞いたことありませんか?
また「漫画は読書ではなく、読解力もつかない」ということも言われます。なぜでしょうか。
私が思うに読解力とは「文字情報を頭の中で映像化する」ことだと認識しています。
そのため、漫画はすでに映像化されてしまっているので読解力がつかないのです。
プロが書く小説は文字を読んでいると自然に頭の中で映像化されると思います。
それを自然に続けることで文字を見たときに映像化する癖がつくのです。
いわゆる本嫌いな人は文字を映像化できないからこそ楽しむことができないのです。
しかしある一定のレベルにたどり着くとどんなに今まで本を読むのが好きな人でも映像化するのに苦戦するときがきます。
それは内容があまりにも抽象的になったときです。
死生観や哲学など日常になじみのない話題はどうしても映像化することが難しいです。
ただおもしろいことにこれも慣れてくると自分なりに咀嚼の仕方がわかってきます。
読解を超えた「解釈」ができるようになります。
文字を文字としてそのまま処理をするのではなく、文字情報を映像にし、簡単な表現に咀嚼することを自分でできるようになることが読解力アップにつながります。
今回もご覧いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくおねがいします。














