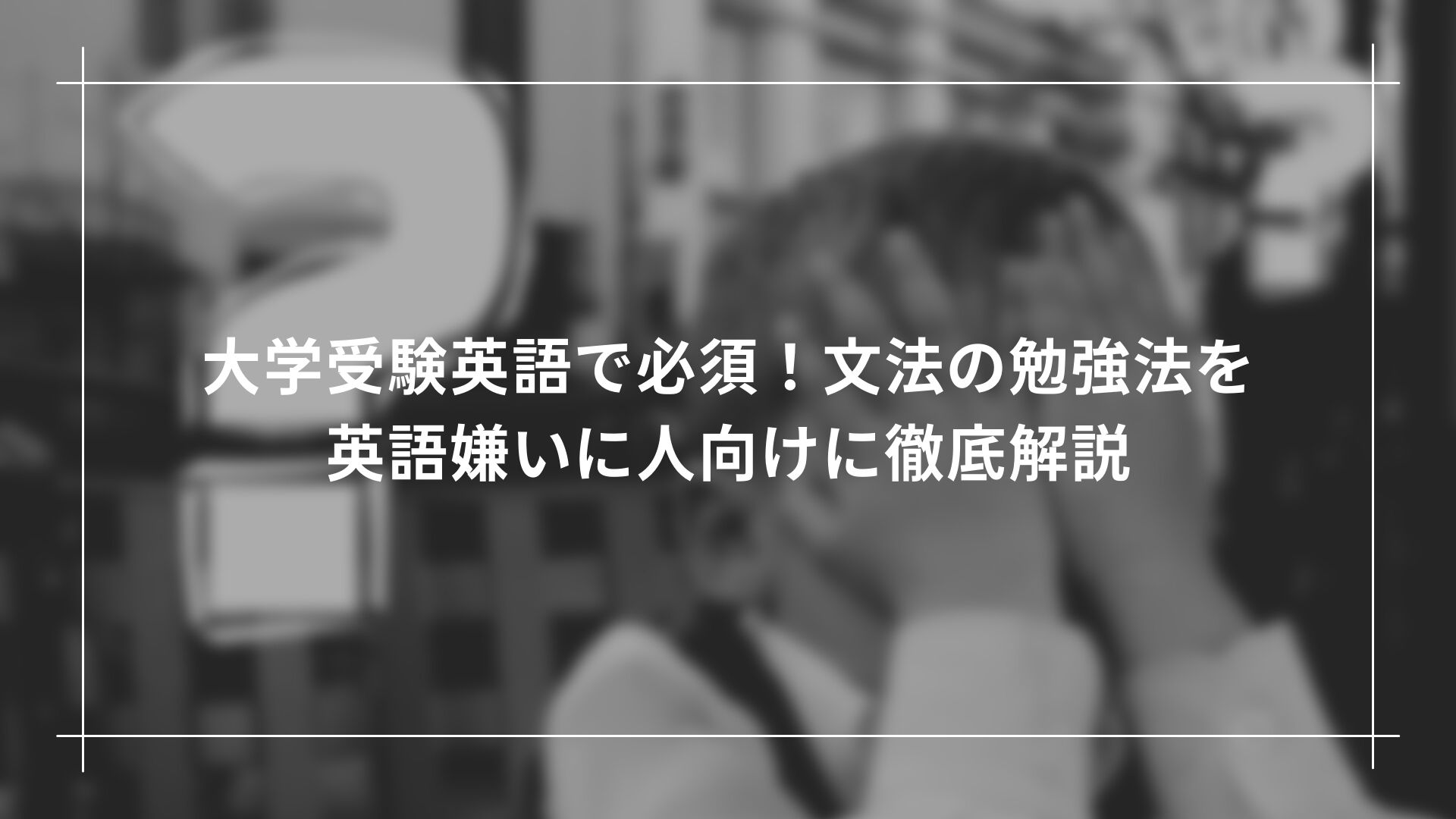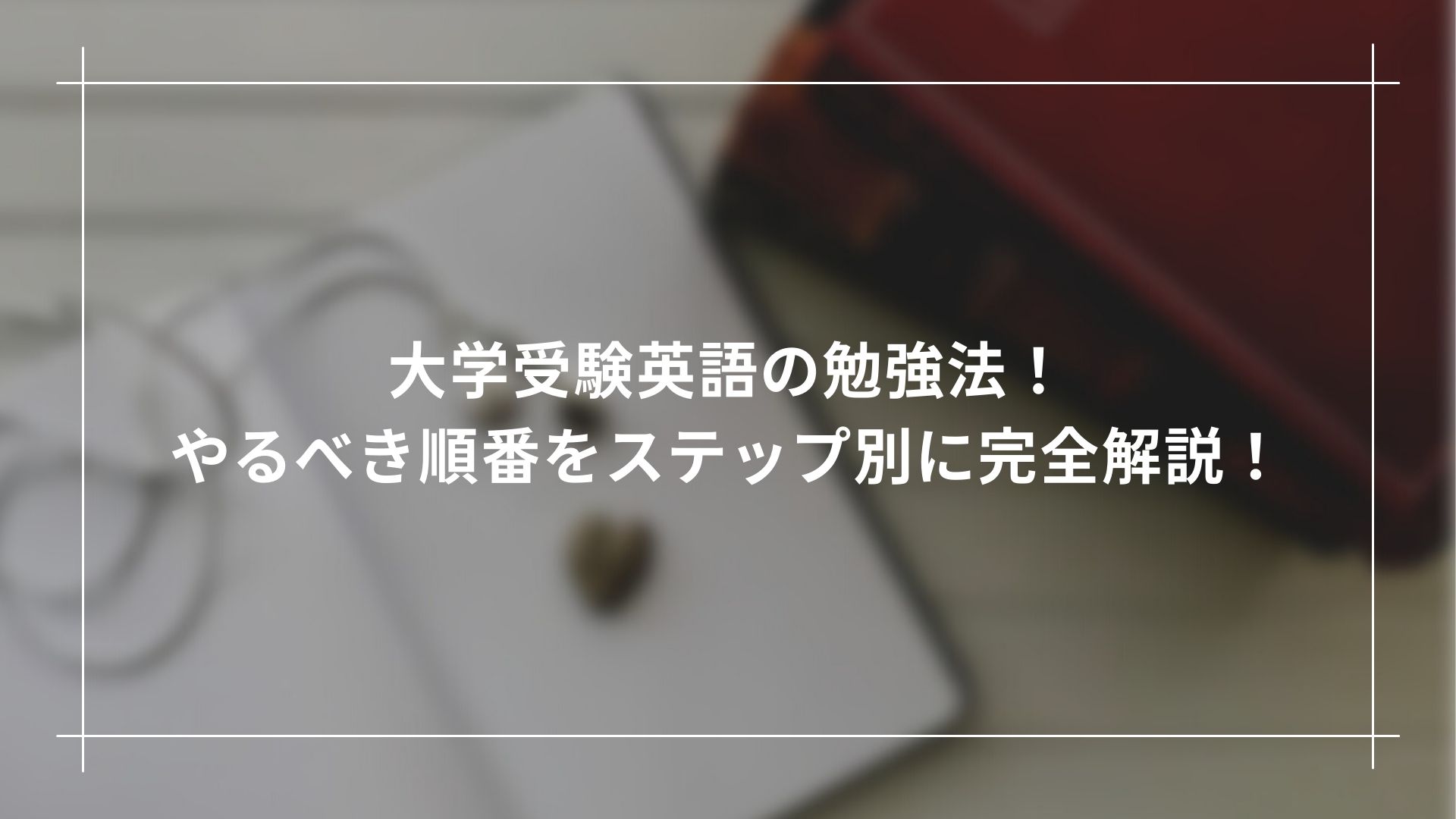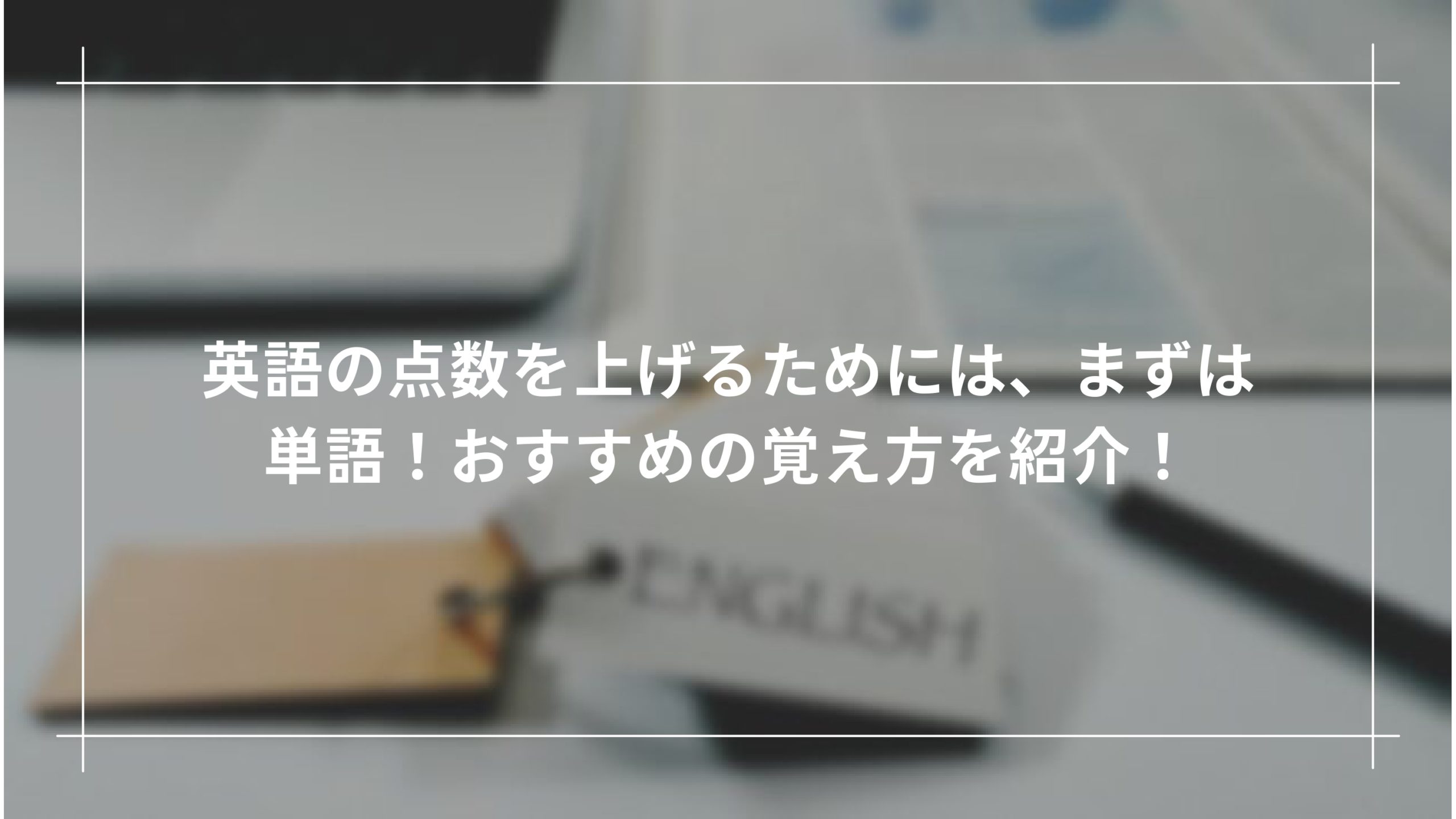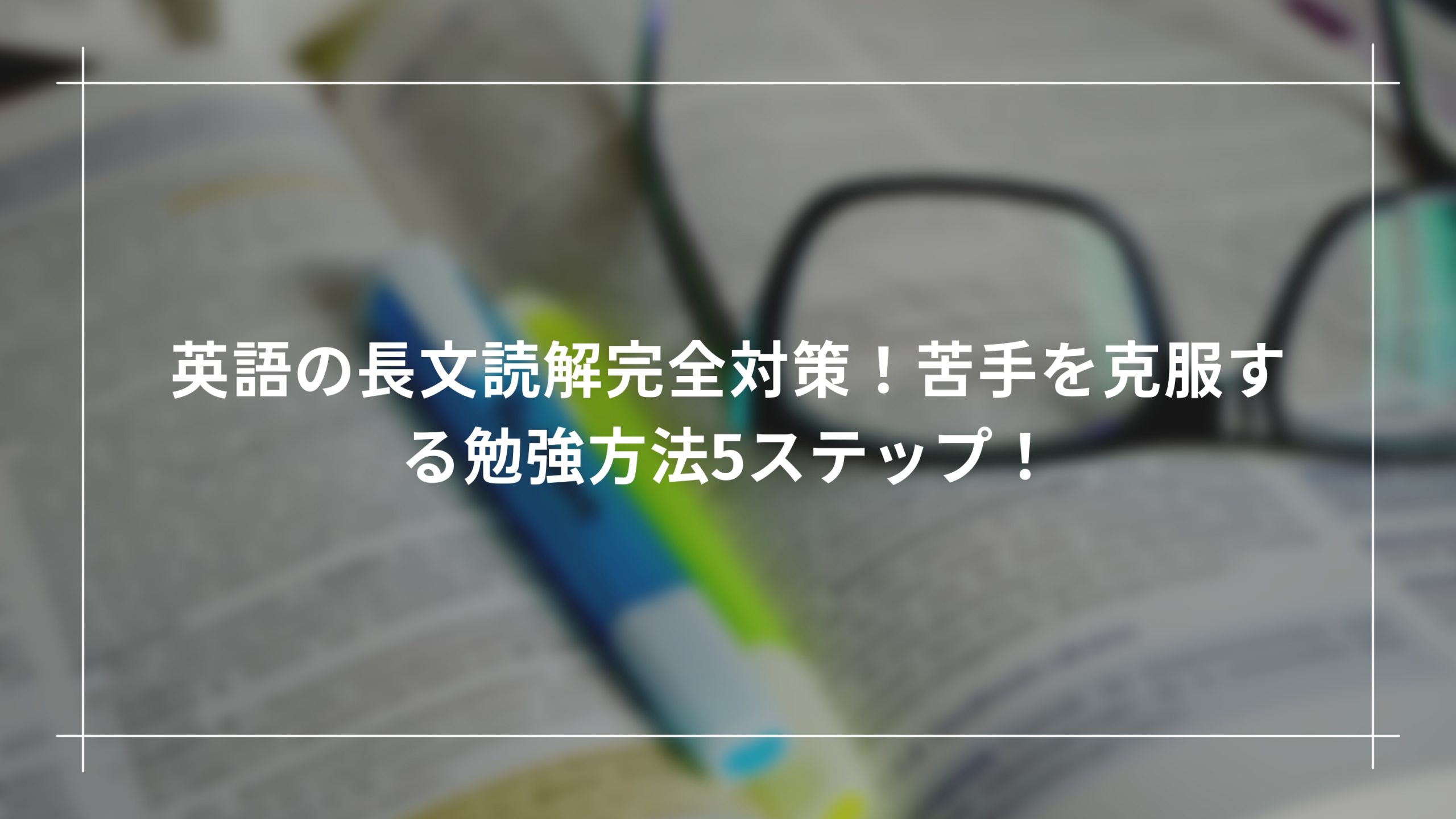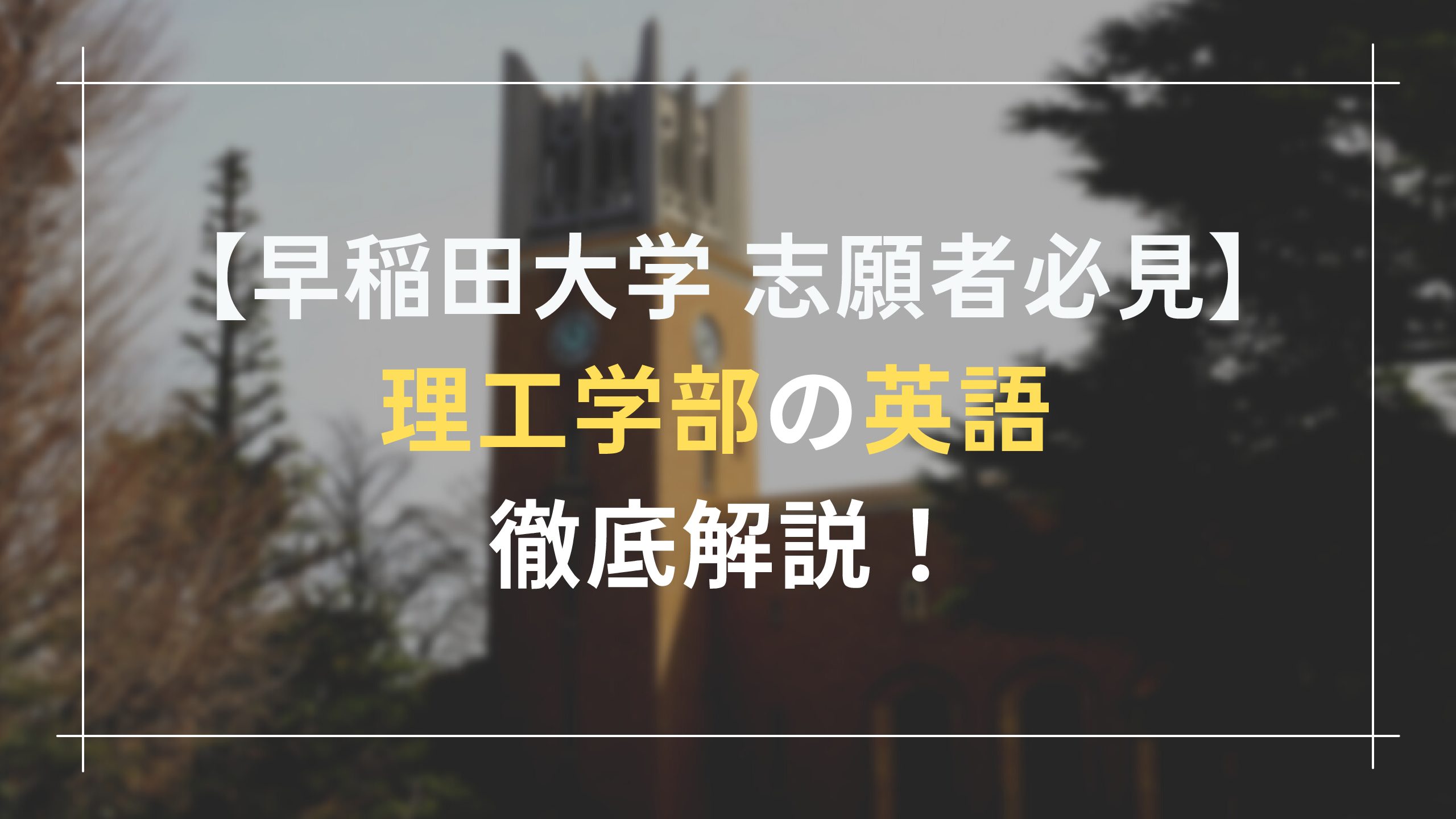
「早稲田の理工学部英語って、どう対策するの?」
「数学と理科はできるけど、英語が難しい…」
早稲田大学理工学部を目指すあなたは、こんな疑問や悩みを持っていませんか!?
本記事は目黒の英語専門塾ENGLISH-Xが監修し、早稲田大学理工学部を志望する受験生のために、英語の傾向と対策・勉強法を解説します。
早稲田の理工学部を目指す方は、最後まで読んで、ぜひ受験勉強の参考にしてください!
※この記事は、7分ほどで読めます。
Contents
早稲田大学理工学部の英語【概要】
早稲田大学理工学部の英語について、概要を確認をします。まずは、全体像をザックリ把握しましょう。
配点と試験時間
理工学部の英語は120点満点で、試験時間は90分です。
理工学部の一般入試は、4科目・合計360点で合否を決めるので、全体の中で英語の点数は3分の1を占めます。
【試験科目と配点】
|
科目 |
配点 |
時間 |
|
英語 |
120点 |
90分 |
|
数学 |
120点 |
120分 |
|
物理 化学 生物 ※2つ |
120点 ※各60分 |
120分 ※各60分 |
全教科で成績標準化がないため、素点がそのまま合否の判断材料になります。なお解答方式はマーク式のため、記述問題はありません。また問題文は、すべて英語表記です。
理工学部英語の平均点は?日本一難しいの?
早稲田大学理工学部の英語を、平均点と難易度の観点から考えてみましょう。以下で、順に詳しく解説します。
理工学部英語の平均点
理工学部英語の平均点は、およそ58〜70点の範囲になります。少し幅を持たせている理由は、以下の2つです。
- 平均点は年によって上下する
- 平均点は学科ごとに算出される
得点率に換算すると、例年48〜58%ほどになります。ただし70点台になることは稀で、最も多い平均点の分布は、約60点(5割)前後です。
正確な数字は、成績開示の希望者のみ知ることが可能で、公表されません。約60点(5割)前後という数字は、あくまで目安だと思ってください。
理工学部英語の難易度
早稲田の理工学部英語は、私立最高峰の難易度です。「日本一難しい」と表現されるのも納得する、ハイレベルな要素の多い問題になっています。
一方で「社会科学部の英語のほうが難しい」という意見もあります。出題傾向や設問が異なるため、単純に比較しがたいですが、どちらも難度が高いことは確かでしょう。
理工学部の合格最低点と英語の目標点
合格最低点から見える、理工学部英語の目標点について解説します。過去問演習をした際の参考にしましょう。
理工学部の合格最低点
早稲田大学理工学部の入試では、学部・学科ごとに合格最低点が算出されます。近年の点数は、以下で確認しましょう。
【基幹理工学部】
|
学系 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
学系Ⅰ |
178 |
198 |
207 |
|
学系Ⅱ |
181 |
219 |
221 |
|
学系Ⅲ |
176 |
213 |
210 |
【創造理工学部】
|
学科 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
建築 |
185 |
218 |
215 |
|
総合機械 |
161 |
192 |
197 |
|
経営システム |
178 |
206 |
211 |
|
社会環境 |
163 |
202 |
202 |
|
環境資源 |
163 |
202 |
197 |
【先進理工学部】
|
学科 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
物理 |
196 |
229 |
230 |
|
応用物理 |
176 |
210 |
210 |
|
化学・生命化学 |
175 |
206 |
207 |
|
応用化学 |
180 |
209 |
202 |
|
生命医科 |
186 |
219 |
219 |
|
電気・情報生命 |
172 |
198 |
196 |
上記の表から、合格最低点は年度によって大きく上下するのが確認できます。
難しい年は45〜55%ほどの範囲に散らばり、易化した年は53〜63%ほどの得点率です。
理工学部英語の目標点
早稲田の理工学部英語は、平均点以上を目標にしましょう。もちろん年によって平均点は上下しますが、5割以上取れれば、十分戦えます。その理由は、以下のとおりです。
- 5割以上で平均を超えうる
- 英語は高得点が取りにくい
- 数学・理科の配点が大きい
得点配分が大きな「理系科目が勝負を決める」可能性が高いので、英語は「ライバルに差をつけられないこと」が重要です。
しかし英語で平均点を獲得するのにも、一定レベルの英語力は必要。理系学部ですが、英語を捨てるのは危険です。粘りの受験勉強で、英語は5割以上を目指しましょう。
早稲田大学理工学部の英語【近年の傾向】
近年の早稲田大学の理工学部英語は、5つの大問で構成されています。さまざまなタイプの設問があり、総合力が問われる問題です。ここでは、各設問の出題傾向を確認しましょう。
大問Ⅰ:読解問題
大問Ⅰには、TextⅠからⅢまで3つの長文があり、理工学部の英語では最も難しい大問とされています。出題の多い設問は、以下のとおりです。
- 内容一致
- 同意表現
- 段落構成
特に3つの長文を関連させた形の内容一致や、本文から推論させる設問が特徴的です。
直近3年の大問Ⅰの総語数は1300語ほどで、決して長くありません。しかし90分で他の問題を解くことも考えると、限られた時間で解く難易度は高くなっています。
また長文のテーマは、科学系・数学系の論説文が多くなっています。背景となる知識があると、読みやすくなるでしょう。
大問Ⅱ:語句整序
大問Ⅱは、語句整序の問題です。本文の文脈に合うように、語句を並び替えて、3番目と5番目に並ぶ単語の組み合わせを選択します。
長文のなかに出てくる英文を並び替える形式なので、文脈を読み取る力も必要ですが、実際は文法・語法の知識が重要です。カッコの前後に合う、適切な品詞を選んで、解答を作りましょう。その後、文脈に当てはまるかを確認すればOKです。
大問Ⅲ:総合問題
大問Ⅲは、問題AとBの2段階構成になっています。それぞれの設問のタイプもレベルも、まったく異なる総合問題です。
大問ⅢのA問題
前半のA問題は、長文の流れに合う単語を選択する空所補充です。ここでは、文法・語法・語彙の力が求められます。標準的なレベルなので、得点源にしたい問題です。
大問ⅢのB問題
後半のB問題は、文整序と段落整序です。それぞれ「5〜6つの文」と「4つの段落」を、自然な流れに並び替える、論理的な英語力が問われます。慣れていないと、ネイティブスピーカーでも間違える難度なので、攻略には対策が必要です。
大問Ⅳ:読解問題
大問Ⅳの読解問題にも、問題AとBの2つがあります。どちらの問題も、本文の内容把握がメインで思考力を問う問題や計算が必要な問題が過去に出題されてきました。
また例年、B問題には図表が挿入され、本文と照らし合わせながら読解する必要があります。なお近年、計算が必要な問題は出題されていません。
科学や数学の専門的な内容がテーマになることが多く、知識があったほうが読解しやすくなるでしょう。限られた時間で正確に読んで考える力が試される問題です。
大問Ⅴ:語彙
大問Ⅴは、2つの英文に当てはまる共通語を補充する問題です。解答を選ぶまでのプロセスが独特なので、出題形式に慣れる必要があるでしょう。解答方式の例は、以下のとおりです。
【大問Ⅴの解答方式の例】
答えの単語が「wise」だった場合、2つの英文のカッコ内に「(w )」と、アルファベットの頭文字が入っています。
「w」の続きのスペルに対応する数字を、表の1〜4から選びます。表は、以下のとおり。
|
Number |
Letters |
|
1 |
a,b,c,d,e,f,g |
|
2 |
h,i,j,k,l,m |
|
3 |
n,o,p,q,r,s |
|
4 |
t,u,v,w,x,y,z |
「w」の続きの「i・s・e」が区分される数字で表すと「231」なので、答えは「w231」です。
年度によって形式変更はあるものの、大問Ⅴで問われる力が語彙力であることに変わりありません。
早稲田大学理工学部の英語対策【勉強法&おすすめ参考書】
ここでは、早稲田大学理工学部の英語対策や勉強法を解説します。おすすめの参考書や問題集も交えてお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
高難度の設問は捨てる意識も重要
理工学部の英語に対しての、意識の持ち方も大事です。理工学部の問題は「少し英語ができる」というレベルでは、高得点が望めません。
難しい設問や時間がかかる設問は、飛ばす・捨てるの判断も大事です。その判断力は、過去問演習を徹底して磨いてください。
英語でリードを広げることが可能なら最高ですが、多くの受験生には難しいシナリオです。すべての問題を解こうとはせず、解ける問題を着実に解くスタンスで問題ありません。
大問Ⅱ・Ⅲを堅実に解く
大問のⅡ・Ⅲは、堅実に解くことが大事です。理由は簡単で、他より解答に時間もかからず、得点を積み重ねやすいからです。
大問Ⅱの語順整序も大問Ⅲの問題Aの空所補充も、早稲田レベルの文法・語法の知識が身についていれば対応できます。
以下の参考書や問題集を使って、学習を進めてください。文法・語法の知識をもとにした、論理的な思考力を磨きましょう。
- Next Stage英文法・語法問題(桐原)
- 全解説 頻出英文法・語法問題1000(桐原)
- 全解説 実力判定英文法ファイナル問題集(桐原)
ただし大問Ⅲの「B問題」となると、話は別です。「文整序・段落整序」は、文法・語法の力を問う設問ではありません。英文の構造や文脈を捉え、思考する必要があり、解答に時間がかかります。
他に解きやすい問題がある受験生は、大問ⅢのB問題は一旦飛ばしてください。解ける設問を解いて、戻ってくるのも大いにアリです。
「文法が嫌い…」「受験に向けて、英語の基本的な勉強法が知りたい」という受験生は、以下の記事もおすすめです!
語彙力を高め大問Ⅴを攻略する
問題Ⅴの対策のために、語彙力を高めて、得点力をUPしましょう。解答形式こそ特殊ですが、慣れてしまえば、得点を積み重ねるチャンスです。
解答になる単語のレベルは標準的ですが、1単語に存在する複数の意味を覚え、問題文をヒントに考える力が必要です。また選択肢から、単語の推測もできます。
もちろん中には難度の高い問題もあるため、全問正解は難しいですが、取れる問題を着実に解きましょう。以下の参考書や単語帳を利用して、徹底的に語彙力を高めましょう。
- ターゲット1900
- 解体英熟語
- 話題別英単語リンガメタリカ
「英単語を覚えるのが苦手…」「英単語を効率よく覚えるコツを知りたい!」という受験生は、次の記事も参考にしてください!
パラグラフリーディングを練習する
早稲田の理工学部を目指す受験生には、パラグラフリーディングの練習をおすすめします。なぜなら論説系の問題と、相性のいい読解方法だからです。
各パラグラフの内容や関係が把握できると、全文を読む必要がなくなり、解答時間を確保しやすくなります。さらに、文脈を捉える力の向上も期待できます。
大問Ⅲの問題B「文整序・段落整序」は、指示語やディスコースマーカー(接続詞や副詞など)を見つけてヒントにすることで、根拠を持って解くのが容易になるでしょう。
他の長文読解を解くときにも役立つ読み方なので、ぜひ練習をしましょう。おすすめの参考書は『パラグラフリーディングのストラテジー1・2(河合)』です。
ただし問題ⅠやⅣの内容一致は、大意を捉えるだけでは解けません。効率よく問題を解くためには、やはり精読力も必要です。
過去問演習までに、基本的な長文対策は徹底してください。以下の問題集を使い、少しずつレベルアップしましょう。
- やっておきたい英語長文300〜1000(河合)
- The Rules1〜4(旺文社)
「そもそも長文読解の問題が苦手…」という受験生には、以下の記事もおすすめです!
早稲田の理工学部英語はしっかり対策して臨もう!
早稲田大学理工学部の英語は、間違いなく私大最高峰のレベルでしょう。高得点は取りにくいので、まずは平均点に負けないことが最優先です。
合格するためには、得点になる問題で着実に正解を積み重ねることが重要です。特に以下の大問は、対策をして得点源にしてください。
- 大問Ⅱ・Ⅲ:文法系の問題
- 大問Ⅴ:共通語補充の問題
また試験問題の中には、難解な難問もあります。取捨選択をしつつ、時間を確保する判断も必要です。過去問演習の際に、必ず意識しましょう。
\ ENGLISH-Xの卒業生が早稲田大学先進理工学部に合格しました!/
ENGLISH-Xの卒業生が、2022年度入試にて、早稲田の先進理工学部に合格しています。合格者インタビューの記事も、ぜひご覧ください。
ENGLISH-Xの授業を体験してみたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。「英語の成績を上げたい!」という、あなたの挑戦を待っています!